誰かに何かを依頼するときは「スキルが発揮できる場を準備する」と考えるとうまくいく
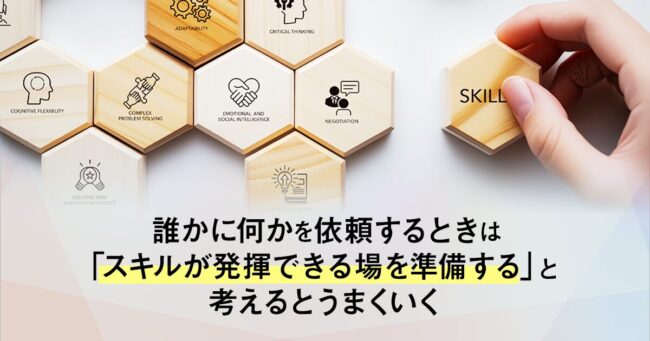
だれかに仕事を頼むときは、「やらせる」という意識でいるとうまくいかないことが多いです。相手を無理に動かすことではなく、その人のスキルや経験が自然と発揮される場を整えるとうまくいくと思ってますので、どんなものかを書いていきます。
指示ではなくスキルを活かす設計をする
思い通りに進まないとイライラすることってありますよね。
個人的な経験でいうと、自分で仕事ができるようになってくる30台前後の頃でしょうか。自分が仕事ができると思っていて、これぐらいなら簡単でしょ?みたいな感じで「やらせて」しまう。そうすると自分基準ですべてを判断してしまうので何もかもダメに見えてしまいます。最終的にはイライラするだけになって「自分がやったほうが早い」となるんですよね。
アフリカのことわざにあるように「早く行きたければ一人で進め、遠くまで行きたければ皆で進め」。これです(「文句が言いたければお前がどっかに行け」と思う)。
なんでこうなってしまうかというと、自分の基準で物事を見ているからです。「自分ならこうするのに」「どうしてこのやり方をしないのか」と感じる瞬間、実は依頼ではなく支配になっていることが多いです。
当たり前のことですが、自分と同じように動ける人などいません。いたらコピー人間なの気持ち悪いですし、違う視点やスキルを持っているからこそ頼む価値があります。
なので、依頼するときは、「どうすればこの人が得意な形で力を発揮できるか」を考えるとうまくいきます。
それが依頼の設計ですね。
場を整えるとは前提を共有すること
スキルが活きるかどうかは依頼前の準備でほぼ決まります。
- なぜこの仕事をするのか(目的)
- 何を目指すのか(ゴール)
- どんな制約や背景があるのか(文脈)
- 誰と関わる仕事なのか(関係性)
- 何をしてほしいのか(期待)
これらの情報を共有するだけで、細かい指示を出さなくても自然と良い方向に進みます。整った場を作ってあげると相手は自分で考えますし、動けるようになりますから。
逆にここが抜けたまま「これをお願いします」とだけ伝えると、相手は迷子になってうまいかないですし、「なんでできないの?」となります。
依頼側の仕事は「コントロール」ではなく「環境設計」なんですよね。
具体的な事例をいくつか
(1)社内での依頼
たとえば社内メンバーに「資料をまとめて」と頼む場合、気心も知れた相手なので察してくれるだろうと思って、多くの人は完成イメージを伝えずに依頼してしまいます。
受けた側は「何を基準に仕上げればいいのか」がわからず、何度も修正が発生します。
「誰に見せる資料なのか」「何を伝えたいのか」を共有しておくと、自然と方向性が合ってきます。目的を理解している人は、指示がなくても考えて形にしてくれます。
- 目的:会議で配布する資料を作るために、A・B・C・Dの書類を整理してまとめる
- ゴール:4つの書類の内容が漏れなく、ダブりなくまとめられており、読みやすくなっていること
- 文脈:来週中にA4で3枚以内の資料に収まるように
- 関係性:部署内でのミーティング用
- 期待:きっちりした資料を作ってくれているのでそのイメージで
これだけで相手は何をどうすればいいかを自分で判断できるようになるので、細かい指示をしなくても、質の高いアウトプットが自然とでてきます。
(2)外部パートナーへの依頼
デザイナーやライターなど外部の人に頼むときは、スキルを引き出す情報の与え方が大切になります。
「参考サイトのようなデザイン」よりも、「このサービスの目的はこれで、ユーザーはこういう人たちです」と伝える方が、相手はプロとしての判断を活かせます。相手の力を信じて任せることで、アウトプットの質が上がります。
- 目的: サービスのトップページでキャンペーンを目立たせてクリック率を上げたい
- ゴール: メインビジュアル1枚+バナー3種をセットで作りABテストに使える状態にする
- 文脈: 既存ユーザーの再訪を狙った施策で全体のトーンは落ち着いた雰囲気にしたい
- 関係性: 継続的にお願いしている外部デザイナー
- 期待: いつも提案の段階から良いアイデアを出してくれているので今回も自由に発想してOK
依頼の「背景」や「期待」、「どう作るか」よりも「なぜ作るか」を共有する。
たったそれだけでスムーズに進みます。
(3)プロジェクト全体での依頼
プロジェクトでは複数の専門職が関わって依頼は連鎖していきますので、それぞれが自分の判断で最善を尽くせるように、全体の文脈を共有しておくことが重要です。
たとえば、Webサイトのリニューアルを進める場合。
- 目的: BtoB向けの新しい見込み客を獲得するため問い合わせ数を増やしたい
- ゴール: 〇月末までに新サイトを公開し問い合わせフォームからのCVRを2倍にする
- 文脈: 製品紹介ページの内容は残すが全体構成と導線を再設計する
- 関係性: 社内のマーケチーム+外部デザイン会社+ライターでチームを組む
- 期待: みんなが自分の専門領域で力を出し合えるように週1で情報共有を行いたい
このように整理しておけば、デザイナーは導線を、ライターはメッセージを、社内メンバーは製品情報を提供するといった感じで、それぞれの得意領域で判断して動けます。
指示書で細かく説明するよりも、プロジェクトの地図を作るイメージでしょうか。
仲山進也さんの「お題設計アプローチ」に見る凸凹を活かす依頼
ここで思い出すのが、仲山進也さんの「お題設計アプローチ」です。
お題設計アプローチは、アオアシに学ぶ「答えを教えない」教え方: 自律的に学ぶ個と組織を育む「お題設計アプローチ」とは(アフィリエイトリンク)に書かれているものです。気になる人、アオアシが好きな人は読んでみて下さい。
書籍の中で仲山さんは、正解を教えるのではなく「お題を出す」ことで、学ぶ人が自分に合った解を試行錯誤の中から見つけ出す仕組みを提唱しています。この考え方は依頼のあり方にもよく似ています。
人にはそれぞれ得意と不得意があり、考え方にもクセがあります。凸凹があるのが自然という考え方。
依頼する側は、その凸凹をならして平らにするのではなく、活かす方向で組み合わせる設計した方がうまくいきます。
仲山さんが言うように、リーダーは「答えを教える賢者」ではなく「お題を出す愚者」であればいいと私も思いますし、依頼も同じで完璧な指示を出すことより、「この状況をどう解くか」というお題を提示するほうが、相手のスキルと個性が引き出されます。
お題設計の本質は、「正解を当てる場」ではなく「試行錯誤を楽しめる場」をつくることだと思っています。
スキルを輝かせる依頼は「信頼」から生まれる
依頼上手な人は相手の力を信じています。
細かく管理するよりも、「あなたならできる」と任せるので、相手もその期待に応えようとし、自然と責任感を持って動きます。
もちろん、相手ができることが分かっていて、ちょっと難しいぐらいの範囲で依頼をします(無理をさせると伸びるという人もいますけどそれはレアかと)。
反対に最初から「できるのか不安」と思いながら依頼するとその不安は伝わってしまいますし、「仕事だからやって当たり前」と思いながら依頼しても、なんで自分がやらないといけないのかと反発されます。
結果として相手も慎重になり挑戦を避けて無難なものしか出てこなくなって、「なんでできないの?」がまたまた出てきます。
信頼がない場ではスキルは発揮されないことを知っておきましょう。
依頼とは相手が輝ける舞台づくり
依頼とはタスクの分担ではなく「舞台づくり」です。
タレントやアイドルのプロデュースみたいなものでしょうか(やったことないけど)。
その人の得意が光るステージを用意すること。背景を整え、役割を明確にし、成果の方向性を示す。そうすれば、あとは相手が自分らしく演じてくれると思います。
「やらせる」ではなく「活かす」。
その視点で依頼を設計すれば、チームの動きが変わり、結果も自然とついてきますので、部下とか外部パートナーが思うように動かないと悩んでいる人は、この記事を参考にしてみて下さい。
