だけどチームがワークしない“集団心理”から読み解く 残念な職場から一流のチームまでを読んだ感想です。
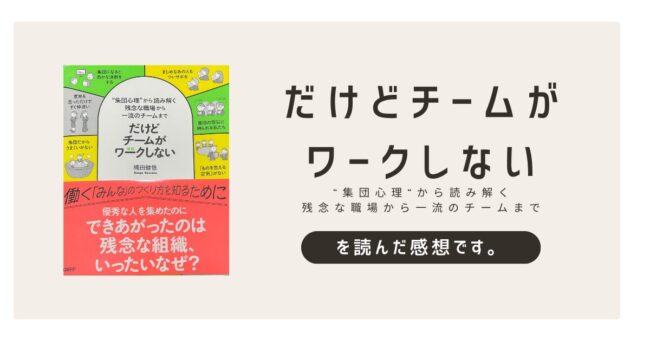
チームワークという言葉がありますが、チームでワークすることはあってもチームがワークすることって意外と少ないと感じてます。仕事柄、いろいろな施策を提案する身でありまして、その施策が実行されないとGA4を使うチャンスもないし成果も出ないのでここに頭を悩ませることが多いです。
ということで、チームをワークさせるための本をいろいろな読んでいるので、その中1つを紹介します。
性格ではなく状況に目を向ける
「みんなで協力すればうまくいく」ってよく言いますよね。でも実際やってみると、なぜか空回りしてしまうことが多いのではないのでしょうか?この本では、その理由を社会心理学の視点からすっきり説明してくれます。
特に印象に残ったのが「性格より状況に注目しよう」という考え方です。ついつい「あの人は消極的だから」「リーダーシップがないから」と、その人の性格に原因を押しつけがちですが、実際は行動を決めるのは性格じゃなくて「状況」なんですよね。状況を変えるだけで、まったく違う動きを見せることがあります。
たとえば会議で発言しない人は「性格が消極的だから」ではなくて「発言しにくい雰囲気」が原因かもしれません。それであれば「発言しやすい会議の仕組み」を作ったほうがいいですよね。締切を守れない人も同じです。「だらしない性格」と思い込むのではなくて、タスク管理の仕組みを工夫すればちゃんと回るケースも多いはずです。性格を変えるのは無理でも、状況なら変えられる。そう考えるとチームの可能性が一気に広がると思います。
チームを支える4つの基盤
著者の縄田さんは「協力・受容・信頼・コミットメント」という集団づくりにおける4つのキーポイントを説明しています。
たとえば協力では、単に「協力しよう」と呼びかけるだけでは不十分でペアワークやバディ制度のように、自然に協力せざるを得ない構造をつくることが大切と書かれていたり、受容についても一度きりの研修ではなく、日常的に人間関係を配慮するような言葉を使うよう促す仕組みを設けるとか。このあたりはエコロジカルアプローチに似ているなと。
中でも「信頼」は印象に残りまして、そもそも信頼は作ろうと言ってもできません。約束を守る文化、失敗を許容する姿勢、透明性のある情報共有などから自然に生まれるものだと書かれています。言動よりも行動、これが難しいけどやらないといけない。
集団浅慮(グループシンク)の恐怖
「集団浅慮(しゅうだんせんりょ)とは、集団のまとまりを追求するあまり、非合理て未熟な意思決定をしてしまう集団の状態です」。と書かれています。事例として2つのスペースシャトルの事故が取り上げられていて、技術的な懸念を持ちながらも集団内での同調圧力から大きな悲劇につながったと説明されています。大きな案件の納期が近くてみんな早く終わらせたいと思っているときに、ここが気になるから…とか言いづらいですよね。日本だと特に「和を乱す」ことはダメなので合わせちゃうときってありますよね。まさにそれ。
ブレインストーミングの話も興味深いです。みんなで集まって話すよりも、一人で出したアイデアを後で集めたほうが質も量も高いということ。確かに、私も自由に発言しろと言われても声の大きい人に流されたり、他人の目を気にして意見を控えたり、発言を待っているうちに萎えてしまったした経験があります。「まず個人で考えてから統合する」やり方は理にかなっていると思います。とはいえ、日本人って答えを求めがちだし、小さいころから答えを出せといわれ続けているので、アイデアとか思い付きで話すのって苦手で、一人ブレインストーミングができる人も少ない気もしますが…。
PM理論と4階建て
リーダーシップ論として紹介されるPM理論はシンプルでとってもわかりやすいです。成果を出す力(P=Performance)と人間関係を維持する力(M=Maintenance)のバランス。面白いなと思ったのは、著者が「M型(甘やかし型)」リーダーの問題点をはっきり指摘しているところです。人間関係はすごく良くて居心地はいいんだけど、成果が出ないチームってありますよね。まさに「ぬるま湯」状態。短期的には楽かもしれませんが、長い目で見れば組織にとってもメンバーにとってもマイナスになってしまうんです。リーダーとして嫌われたくないという感情が先に出てくるとこうなりがちです。
かといって、無駄に厳しくしても嫌われるので難しいのですが…。どうすればいいかのアドバイスは本を読んでみて下さい。
「チームワークを4階建ての建物」に例える説明もわかりやすかったです。基盤となるリーダーシップから始まり、心理的安全性が2階、目標共有とフィードバック・相互協力が3階、最上階に「チーム学習」があります。この構造を知っておくと、自分のチームの現状が診断できるのでやるべきこと、どこまで行ったら次に進めばいいのかもわかります。いきなり上の回からやろうとしがちですが、何事も土台というか基礎が必要ですよね。プロレスでいうところのスクワット1000回みたいな感じ。
心理的安全性と見える化
心理的安全性はよく耳にする言葉ですが、大事なのは「心理的安全性=ぬるま湯ではない」ということです。心理的安全性の高いチームでは、「それは違うと思う」「このやり方じゃうまくいかないかもしれない」といった率直で厳しい意見が飛び交います。反対意見を言っても人間関係が壊れないし、むしろ議論を深める材料として歓迎されます。言いたいことが言えずに表面上の安全性はまったく安全ではなくて、周囲をうかがいながら怯えている感じです。最初からこうしようと思ってもダメで順番があります。先ほどのPM理論とか4階建ての1階にあたるリーダーシップをクリアしておかないといけません。
「見える化(あのツールではない)」の話も納得でした。見える化って監視のためにやる人が多くなりがちで、それをやってしまうと「信頼されていない」というメッセージになってしまいます。これまた、怯える人が増えます。反対に信頼を前提にした見える化は「お互いの状況を把握して助け合える仕組み」になります。たとえばタスクの進捗が共有されていれば「ここ手伝おうか」と自然に声をかけられる。管理されている感ではなく支え合うための道具になるわけです。
実践のステップも具体的でです。リーダーが自分の失敗を開示する、定期的にチームで振り返りをする、いきなり全社でやるのではなく小さなチームから試す。こういう現実的な方法が示されているので「読んで終わり」にならないのが良いところです。
まとめ
チームが機能しない理由は人材の能力不足やリーダーの資質不足ではなく、集団心理の罠にあるということなんですね。この本は罠を理解し、抜け出す具体的な方法を教えてくれます。「どうしてうまくいかないんだろう」と悩んだことがある人にとっては参考になることも多いと思います。
仲山進也さんのチームビルディングの内容と共通しているところも多いので、そちらについても後日紹介できればと思います。
