AIを使うとバカになるって記事を見かけるけど、個人的には頭が疲れるのです。それはなぜかと考えてみました。
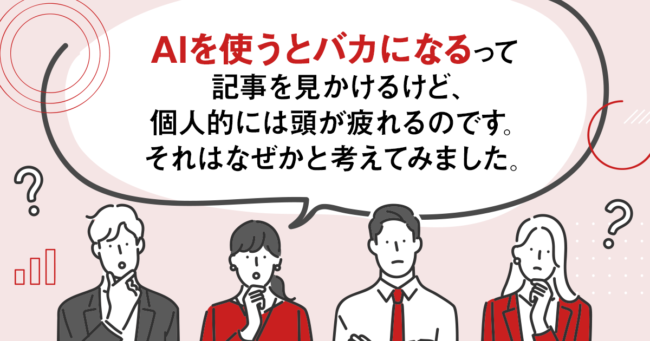
AIを使って何かするとものすごく頭が疲れます。電流を流されて無理やりに回転数を上げられて煙が出る感じ。しかし、世の中にはバカになるという記事が多いです。なぜでしょうね?
こんな記事を読んだ
- ChatGPTを使うと脳がサボる?──MIT、エッセイ執筆中に脳活動が最大55%低下することを確認 | Ledge.ai
- AIとの協働で見落としがちな思考力の変化
- 生成AIで馬鹿になる 知性と創造性を守りつつAIと付き合う方法|住太陽
AIチャットボット「ChatGPT」を使用しながらエッセイ課題に取り組んだ参加者の脳活動が、他の手段を用いたグループよりも著しく低下したとする実験結果を査読前論文として、arXiv上に発表した
ChatGPTを使うと脳がサボる?──MIT、エッセイ執筆中に脳活動が最大55%低下することを確認より引用
だそうなんです。
イントロ文にも書きましたが、実際に私がAIと一緒に作業している時の感覚はちょっと違います。「バカになる」どころか、AIとやり取りしながら仕事をすると、ものすごく頭が疲れるんです。ラクどころじゃない。むしろ考える量が増えているように感じます。
疲れる作業とラクになる作業の違い
これがどこにあるのか?と考えてみると、AIと一緒にドキュメントをまとめる、提案書を作る、記事を書く、こういった作業では、とにかく頭が疲れます。どういう情報を盛り込む、何を削ぎ落とすか、順番はどうするか、誰に向けてどういう語り口にするかといったいろんなことを考えますし、AIが出してきた案に対しても「これは本当に使えるのか」「もっとよい表現はないのか」と考え続けますので。
この記事でもそんなことを書きました。
AIに助けてもらいながら自分の言葉で記事を早く書く方法
その一方で、エクセルでの分析作業やパワーポイントの図解づくりは、AIに任せることでかなりラクになりました。数字を集計したり、グラフを作ったり、表現を整えたり。こういったところは「手段」なのでAIに任せて省力化できています。というか、自分が想像した以上のものが出てきて大変助かっております。AIがない時代には戻れない…、ん?これがバカになるということか?
この違いは何なのか。
よくよく考えてみると、方向性が決まっているけど答えが決まっていないものは疲れる作業、答えまで決まっているものはラクになる作業なのかなと。
ドキュメント作成や提案書作りは「自分の考え」や「伝えたいこと」を形にする仕事で、方向性はあっても最終的な答えは決まっていません。ここはAIがいくら優秀でも、こちらの頭を使わないとうまくいかない。だから疲れる。分析や図解は答えが決まっている「手段」的な仕事なので、AIに任せても問題ないし楽になる。
疲れるときの詳細
疲れる理由は大きく2つあると思ってます。
ひとつ目は問いの立て方に気を使うこと。 事実確認や仕様について聞くと、AIは曖昧な答えや間違った情報を教えてきます。一方で「構成はどう?」といういい加減な質問でも、全体の構成や意味については的確に回答をしてくれます。なので、事実確認は自分で調べるから今までやってきたように、いろんなサイトで調べて自分でも試したりして、自信が持てるまでは断言ができません。構成整理はAIに任せることができるんだけど、聞き方を間違うと変な方向に行くので毎回「どう聞こうか」を考えることになります。
ふたつ目はAIの提案についていくのが大変なこと。 自分の思考よりもはやい速度で想像していないものが出力されるので、それを理解して判断するのに脳のリソースを使います。東大卒のエリートが難しい言葉一気にまくし立ててくるイメージです。「どうしますか?」とか「こんなこともできますよ?」と言われたところで、中身がわかってないから理解で必死です!という状況。かといって簡単にしてもらうと、小バカにされた感じもしてイラっとするのですが(笑)。
まとめ的なもの
最近よく言われる「AIを使うとバカになる」というのは、本来考えるべきところまでAI任せにしてしまう場合の話です。記事をまるっとAIに書かせてそのまま出したり、データを見ずにAIの要約だけ読んだりする使い方だと確かに「バカになる」方向に行きます。しかし、AIを「考える相手」として使い、問い返してもらったり構造化を助けてもらったりする使い方なら、むしろ考える量が増えて「頭が疲れる」方向に行くのだと思います。
これってコンピュータが出てきたときにも言われてましたよね。
いつの時代も、考える人は生き残れるということでしょうか。
と言いつつも、「○○について考えて」と指示してしまうわけですが。
