AIを使ったデータ分析で中小企業と大企業の違いをなんとなく考えてみました。
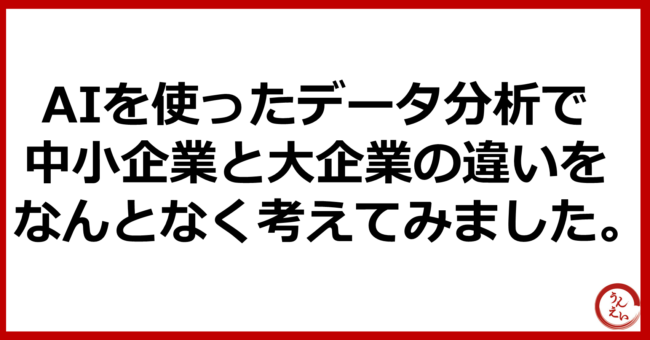
AIを使ったデータ分析は、小規模サイトと大規模サイトで戦い方がまったく違うのかな?と思ってます。小規模サイトはAIを使ってデータを深く読み解き、大規模だと大量のデータでAIを動かす感じかと。このあたりの違いを知っておかないとセミナーに参加したり、本を読んでも間違った方向に行ってしまいそうなので、小規模サイトを基準に考えていることを書いてみます。
小規模サイトでのAIを使ったデータ分析
自分のやり方をAIで手順に
自分の解析フローをドキュメントにして、AIに読み込ませるだけでも十分に活用できます。GA4の1つのレポートのデータなど限られたデータを入力するだけで、AIは思った以上に答えを返してくれます。
こんな手順です。
- 自分の解析フローで解析しながら手順をメモ
- 一通り終わったらわかりづらいところを補足
- 生成AIにまとめてもらう&改善点を聞く
- 何度か繰り返してわかりやすく
そんなに難しくないのでやってみて下さい。
自分の解析フローがドキュメント化されて他の人も使えるようになるのもメリットです。
AIに読み込ませて「1ステップずつ教えて下さい」みたいに聞く
これをやってうまくいけば手順書がちゃんとできていますし、いまいちわかりづらいとなれば手順書を直せばいいです。
繰り返してくと本当にわかりやすい手順書&分析結果が出てきますので、詳しくない人でも改善点がわかって施策を実行することができます。
それをやってくれる人がいない!という場合は、世の中にある説明記事をNotebookLMでまとめて、手順化してやってみればよいと思います。同じようにやっているとうまくいかない部分があるのでそこを修正。
勉強もできて効率化もできて一石二鳥です。
分析を進めると出てくる「もっとデータ欲しい」欲求
これがうまくいくと、次は「このデータも欲しい」と思うようになります。
検索のデータ、広告のデータ、メールマーケティングのデータ…。欲しいデータは無限に広がっていきます。「同じように分析したらどんな改善点が出るのだろう?」という興味と「自分がやっていることがまとまっていく」喜びみたいなのが出てきますのから。
こうして頭の中では理想的な分析環境がどんどん膨らみますが、現実は時間もリソースも限られています。
特に小規模サイトの担当者は、一人で複数の役割を担っていることが多いため、新しいデータを取得するための時間を捻出するのが難しいです。APIの設定やデータの整理、分析フローの構築など、やるべきことは山ほどありますが、すべてを完璧にやろうとすると分析自体が進まなくなります。
名前を付けるのなら「あれもこれも症候群」でしょうか。AIで集計や分析が楽になり、できることが増えますので、データを全部そろえようとして中途半端に終わってしまう。実際には今あるデータだけでも改善につながることが多いのに、完璧を目指すあまり止まってしまう。こんなこともできる!あんなこともできる!と思えば思うほどやりたいことが増えて収集つかず…。
大切なのは優先順位をつけることで、今の課題解決に必要なデータは何か、取得コストに見合う効果はあるのか、一つずつ確実に広げていくことが、最終的には一番効率的なやり方になります。
データが集まったときの落とし穴
それでもデータを集めていくと、それぞれで分析フローを作りたくなります。上記のようにフローが固まれば生成AIで簡単に分析できてしまいますから。
ですが個別最適に走りすぎると、全体像を見失い「改善しているのに成果が出ない」という状況に陥ります。
SEOでは「順位が上がった」し、広告は「CPAが下がった」、メルマガは「開封率が改善した」。それぞれ成功しているのに、売上や問い合わせ数は横ばい。現場ではよくある話です。
原因はいくつかあります。
施策同士の相互作用を見落としていると、SEOで上位表示されたキーワードと広告で狙っているキーワードが重なっていて、結局はトラフィックを食い合っている。全体のボトルネックを見逃していると、流入は増えているのにコンバージョン率が落ちている、新規顧客は増えているのにリピート率が下がっている、といったことになりがちです。
さらに厄介なのは、改善活動そのものがリソースを分散させてしまうことです。あちこちで小さな改善を重ねているうちに、本当にインパクトのある施策に集中できなくなる。「忙しくやっているのに成果が出ない」という典型的な状況です。
解決するには、定期的に全体を見直すことです。週次や月次で「施策ごとの改善と全体KPIへの影響」を振り返り、個別最適に陥っていないか確認する習慣を持つことが大切です。個別最適の罠から抜け出し、全体KPIに直結する施策を見極めることが、次の成長につながります。
全体を見ろとかKPIを意識しろといってもなかなか難しくて、ここまでの経験をして初めてわかることも多いと思います。なので、上司などは必要なステップだと思って細かいところもやらせてあげてほしいですね。
データがどんどん欲しいけど企業規模で大きく変わる
全体が見られるようになって分析を進めていくと、もっと深いデータが欲しくなります。代表的なのがデモグラフィックデータや顧客データです。ユーザーの属性や購買履歴を加えることで、さらに詳細な分析ができるのではないかと考えるようになります。
ただし、小規模サイトと大企業では事情がまったく違います。小規模サイトなら「顧客データを使いたい」と社長に話せば、その日のうちに「やってみて」と言われることもありますよね。システム担当と分析担当が同じ人だったり、隣の席にいたりするので、すぐに権限が付与されます。機動力の高さが強みです。
一方で大企業の場合は、個人情報保護や情報セキュリティの観点から厳格なルールがあります。法務部門のチェック、システム部門との調整、利用目的の明確化、研修の受講など、クリアすべきハードルは多いです。申請から承認までに数ヶ月かかることもあり、その間に現場は手を止めざるを得ません。
さらにデータが部署ごとや代理店ごとに分散しているため、まとめるのにも大きな労力が必要です。マーケティング部門がウェブサイトのデータを管理し、営業部門が購買データを持ち、CS部門がサポートデータを抱えていて、広告のデータは代理店が握っている。このような状況では全体を統合するだけでひと苦労です。
こんなときは「完璧なデータを待たない」ことかなと思います。
すべてのデータを集めてから分析しようとすると、半年から1年かかってしまうこともあります。その間に市場は変化してしまいますから。限られたデータでも推測できることを積み重ねていく方が、現実的で成果につながりやすいですよね。
小規模サイトは機動力を生かして素早くデータを取りに行く。大企業は長期的に基盤を整えながら、使える範囲のデータで分析を進める。それぞれに合ったやり方があるんじゃないかと。
小規模は綺麗さを、大規模は量とお金で解決!?
データ分析と聞くと「まずはデータをきれいに整えないと意味がない」と考えますよね。「Garbage in, garbage out」という言葉があるように、汚いデータを入れれば汚い結果しか出てきません。特にデータ量が限られる小規模サイトでは、この考え方がとても重要です(データとは言えないようなデータってよくありますから…)。
月間1万セッションのサイトで100セッションの計測漏れやミスがあれば、それだけで1%の誤差になります。この誤差が広告の成果やSEOの改善を判断する際に大きな影響を与えることもあります。そのため、小規模サイトではデータを丁寧に整え、精度を確保することが求められます。
大企業は数百万セッションのデータを扱いますから、多少のノイズや計測漏れがあっても、全体の傾向を把握するうえでは大きな問題にならないかな?と思ってます。むしろ細かい整備に時間をかけすぎることで、意思決定が遅れてしまうリスクの方が大きそうな感じす。
最近は、多少汚いデータでも量があればAIがパターンを見つけてくれるツールも増えてきましたし、データを放り込んだらそれなりに綺麗にしてくれるツールもありますし。100%きれいなデータを来月に揃えるより、80%の精度でも今日判断できる方が価値がある場合もあるでしょうから、綺麗さにこだわりすぎなくても、量とお金で解決してしまえば良いと思います。
ただし業界や組織の文化によって、重視すべき点は変わります。金融や医療のように規制が厳しい業界では、データを粗く扱うことはできませんしね。
大切なのは「精度」と「スピード」のバランスを現場に合わせて最適化することでしょうか。
小規模と大規模での違い
同じAI分析でも、小規模サイトと大企業ではやり方がまったく違うと思います。
どちらが正しいかではなく、それぞれの立場で最適なやり方が変わるということですね。
小規模サイトは限られたデータを徹底的に活用し、一人でも回せるフローを作ることが大切です。大企業は部署間の調整や承認フローを前提に、不完全でも意思決定に使えるデータを素早く出すことが求められるでしょう。
小規模の強みは機動力です。朝思いついたアイデアを昼に検証し、夕方には実行に移せます。大企業の強みは安定性と継続性です。個人のスキルに依存せず、組織として分析能力を蓄積できます。
ただし、真似をしてもうまくいきません。小規模が大企業の真似をして複雑な仕組みを作っても運用できずに破綻します。大企業が小規模の真似をして属人的な分析に頼ってしまうと、持続性がありません。
こんな判断でしょうか
月間セッション数が10万未満、担当者が3人以下、意思決定者との距離が近いなら小規模サイト型かなと思います。月間セッション数が100万以上、複数部署が関わる、承認プロセスが複数段階あるなら大企業型。
あとは使えるデータの種類でも変わるでしょうか。ウェブサイトのデータだけなら大したことなくても、それ以外のデータを使うようになってくると個人やちょっとした生成AIでは無理で、何らかのデータ基盤が必要になってきそうですよね。
それ以外に考慮するなら施策の実行スピード。
小規模だと予算も少ないのでチャレンジしづらいでしょうから、ホントに細かいことからこぢんまりやる。失敗した時に何か言われる可能性も高いので、アイデアはたくさんあるけど可能性が高そうなのを探さないといけない。お金にかかわらない部分は早くても、お金にかかわる部分が急に遅くなるのが小規模です。
大規模で予算があれば大きなミスだけに注意して施策の数で勝負することもできますよね。施策の数が増えれば知見もたまって精度も上がりますし。準備には時間がかかってもやるとなったら早いのが大規模ですし、うまくいけば横展開して一気に…ということもあります。
AIで何でもできそうな世の中とはいえできることには限界がありますし、人間がやることも増えてきますので、より調整力とか政治力が大事になってくるのかな~と思ってます。
AIは素直、人間は面倒ってことかも。
うちはこんな感じでやっている、大企業はまったく違うなどあると思いますので、ご意見ご感想などお待ちしております。
